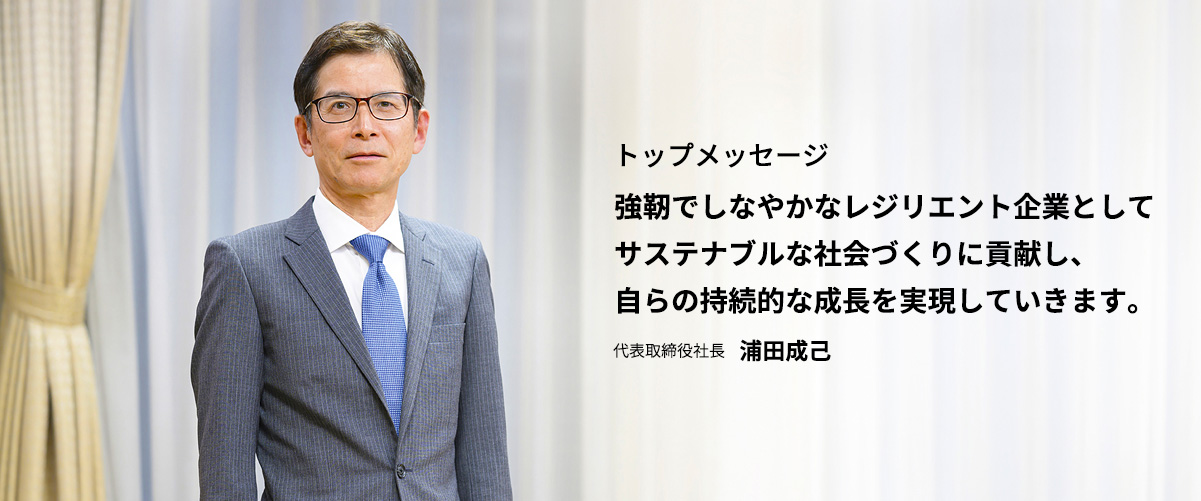

一世紀にわたるモノづくりの精神を基盤に
次の100年を見据えたさらなる挑戦へ。
変化する事業環境を捉えて、競争力を強化する
当社を取り巻く事業環境は、依然として不確実性の高い状況にあります。原料であるニッケル価格の急激な変動をはじめとする資源・エネルギー価格の高騰や地政学的リスクの高まり、国内では少子高齢化による労働力不足、さらには為替変動や国際的な規制強化など、複合的な外部要因が当社の事業活動に影響を及ぼしています。
こうした環境のもと、2024年度の業績は2023年度比で減収減益の結果となりました。減益の要因としては、主原料であるニッケル価格が下降基調に転じたことで販売価格が下落したことや、高機能材部門の製品需要が減退するなど製品構成の影響によるものです。また、一般材・高機能材ともに販売数量は増加したものの、期初目標には届きませんでした。
加えて、業績に影響を与えた要因の一つとして、主要市場、特に中国における環境変化が挙げられ、柔軟かつ迅速な対応が求められています。中国市場では経済の停滞に伴いステンレス需要が減退しています。また、太陽光関連プロジェクトの遅延などにより高ニッケル耐熱材の販売数量が減少するなど、海外売上高の約4割を中国向けの高機能材分野が占める当社にとっては大きな影響となっています。こうした状況を受け、他分野への展開や中国以外の海外市場の開拓を進めていきます。
さらに、中国経済の停滞は、低廉な一般ステンレス鋼の国内市場への流入圧力につながっています。そこで当社は、納期・品質の安定化やアフターサービスの強化、輸入材では代替が難しいニッチな鋼種やアイテムの比率を高めるなど、非価格面での差別化を図るとともに、適正な価格設定に対するお客さまのご理解をいただくことで、持続的な取引関係の構築をめざしています。営業本部に在籍していた頃から現在に至るまで、多くのお客さまとお話しするなかで実感しているのは、当社の強みとは、多様なお客さまとの密なコミュニケーションを通じて、きめ細かな営業・デリバリー体制やニッチなニーズに対応できる提案力を絶えず強化し続けていることです。引き続き、こうした価値提供を行ってまいります。
一方、米国市場については、関税政策の動向を注視しています。米国向けの売上比率は2%程度であり、直接的な影響度は大きくありません。しかし、一部顧客への販売ではすでに販売数量に影響が生じており、今後も先行きが見通ししづらい状況にあります。さらに、当社の販売先で加工されたものが米国に輸出されるケースもあることから、他の地域も含めて需要変動にはこれからも警戒心をもって対応していく必要があります。なお、米国の関税政策についてはマイナスの影響だけとも言えません。当社の競合となる米国メーカーも原材料輸入において関税がかかることになれば、その分コストアップとなる可能性があります。つまり、米国以外の市場では相対的に当社の競争力が高まるということです。中国経済の減退も踏まえ、この機を活かして今後はより多様な国・地域へと市場を広げていく方針です。
中期経営計画の主要施策を着実に実行
これら事業環境を踏まえつつ、「中期経営計画2023」の基本戦略〈1〉「高度化する市場ニーズを追求し新たな価値を生み出す産業素材の開発・提供」で掲げた高機能材の拡販を着実に推進しています。中国は景気減速や金融不安などを抱えて調整局面に入っているものの、巨大な市場である事実は変わりません。オイル・ガス分野の需要の高まりや今後の水素関連分野の拡大、将来的な太陽光関連需要の回復を見据え、引き続き高機能材の販売を強化していきます。ただし、今後の当社の成長とリスク分散の観点から、中国市場のみに注力するのではなく、経済成長の著しいインドや、インドを足掛かりとした中東など周辺地域への高機能材の拡販を重要施策として取り組みを強化していきます。
その一環として、2025年8月にはインドに現地法人を開業しました。インドの魅力は世界最大の人口を擁することで、内需拡大によりインフラ整備やエネルギー関連への投資拡大が見込まれます。また、当社は競合である欧米企業よりも地理的に近いことから、納期面で優位性を発揮することができます。実際、排煙脱硫装置や、中東での環境・エネルギー関連向けの需要は堅調に推移しています。
私自身、インドにおける営業活動を経験したことがありますが、非常にタフな交渉力が求められます。商談が長期化することも多く、出張ベースでの対応には限界があります。そのため、現地に拠点を構え、相手の立場を踏まえながら説明、提案を重ねて信頼関係を築いていくことには大きな意味があり、今回の現地法人の設立を機に、こうした対話を通じてさらなる需要捕捉に努めていきたいと思います。
成長分野としては、水素インフラに注目しています。水素環境下で使われる材料には、さまざまな条件下での試験値が求められます。現在、試験は外部委託していますが、自社内でノウハウを積み重ねていけるよう、川崎製造所の構内に水素環境での材料評価試験場の導入を進めており、2026年3月末には完成予定です。
基本戦略〈2〉「技術の優位性を高め市場環境の変化に対応する効率的な生産体制の構築」で掲げる生産体制の強化に関しては、2024年12月に最新鋭の技術を装備した新冷間圧延設備が本格稼働しました。これまで当社の冷間圧延工程は、高機能材や板厚が薄い製品など製造負荷の高い製品が多くなると生産効率が低下していましたが、新しい設備ではこうした課題が解消し、品質や生産スピード、安全性が向上します。また、圧延時に発生する油煙の捕集能力を向上させることで作業環境も劇的に改善しており、従業員の働きやすさや定着率の向上につながっています。
大江山製造所におけるカーボンレス・ニッケル製錬の取り組みも着実に進捗しています。これは従来の輸入ニッケル鉱石や石炭を主体とした製錬手法から脱却し、リサイクル原料や再生可能エネルギーを活用する取り組みで、2030年度における大江山製造所のCO2排出原単位を2013年度比で7割削減することを目標に掲げています。リサイクル原料の多様化は、エネルギー原単位の改善や調達コスト削減など競争力向上にも直結する重要な施策であることから、現在、製造現場の技術スタッフと研究部門が協力して約200種あるリサイクル原料に関する知見を得るための試験を実施しています。また、フェロニッケル※を製錬するキルン(回転式の窯)は24時間連続操業であることから、休止中の実機を使って年数回のペースで大規模な試験を継続しています。こうした取り組みによって、2024年度のリサイクル原料比率は58.3%に達しました。さらに、今年の7月にはキルンの燃料を石炭からLNGや再生可能燃料へシフトするための工事が完了し、8月から操業を開始しています。
※ 鉄とニッケルの合金で鉄鋼製品に用いる中間原料の総称
多様な人材の活躍と成長を支える職場づくりを推進
持続的な成長を果たしていくうえで人材は最も重要な経営資本です。人材力をいかに高めていくかは企業にとって永遠のテーマであり、当社では事業の持続的成長を視野に多様な人材の採用・育成に取り組んでいます。そのなかで注力しているテーマの一つが、女性活躍を含めた多様な人材の活用です。事業環境が激しく変化するなかで競争力のある提案、柔軟な対応をしていくためには物事を多角的にとらえ、新たな発想、アイディアを生み出していく必要があります。そこで当社は、総合職採用の女性比率を20%以上にすることを目標に掲げ、採用・育成に取り組んでいます。また、高機能材の海外への拡販を担うグローバル人材の拡充も急務であり、キャリア採用も含めた積極的な採用活動を行っています。
さらに、採用した人材がモチベーションを高め、持てる実力を発揮しながら成長できる環境を整備していく必要もあります。2023年度にスタートした新人事制度は、こうした課題を念頭に置いて制定したもので、年功序列によらない実力本位の登用、公平で納得性のある評価に基づいた処遇の実現をめざしています。また、組織の担い手である従業員を対象にサーベイを実施し、現状把握および組織としての課題の見える化・共有化をしながら新たな制度設計に活かし、社員の満足度向上につなげていきたいと考えています。
ガバナンスを強化し、意思決定のスピードと質の向上を図る
当社は2025年6月、コーポレート・ガバナンスをさらに強化していくために監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより取締役会の監督機能を強化し、監査等委員会の適切な監督のもと、経営に関する意思決定を迅速化させることが可能となりました。今後は、取締役会の権限のうち一定の権限を執行側に委ね、経営計画や戦略等に関する、取締役会の審議を充実させていきたいと考えています。
創立100周年の節目にあたり、これからもステークホルダーの皆さまとの関係を強化し、社会や地球環境との共生・調和を図りながら企業価値向上をめざしていくことをお約束します。そして、新たな100年に向かって、私たち現役世代も次世代の社員も、誇りをもって働くことができる企業づくりに邁進してまいります。ステークホルダーの皆さまには、引き続きご理解・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

